九谷焼(くたにやき)
バリエーション豊かな絵付が鮮やかで、力強い加賀百万石を象徴する磁器。
豪快な絵模様、多彩な技巧の数々。「日本の油絵」と呼ばれる古九谷、青手をはじめ、加賀藩が育てた九谷焼は見る人を圧倒する。
九谷焼は石川県南部の金沢市、小松市、加賀市、能美市で生産される色絵の磁器で、その源流は古九谷と呼ばれる色絵磁器であると言われる。この伝統的な手法をベースに、現代感覚を盛り込んだ作品が多い。
九谷焼の歴史
九谷焼のルーツ
加賀藩の支藩の大聖寺藩領の九谷村で良質の陶石が発見されたのを機に、藩士の後藤才次郎を有田へ技能の習得に赴かせた。
帰藩後の明暦初期(1655年頃)、藩の殖産政策として始められるが、約50年後突然廃窯となった。理由はいまだに推測の域を出ていない。
窯跡は加賀市山中温泉九谷町にあり、1号窯、2号窯と呼ばれる2つの連房式登窯と、19世紀に再興された吉田屋窯の跡が残っている。
古九谷
古九谷と呼ばれる磁器は、青、緑、黄などの濃色を多用した華麗な色使いと大胆で斬新な図柄が特色で、様式から祥瑞手、五彩手、青手などに分類されている。
祥瑞手は、赤の輪郭線を用い、赤、黄、緑などの明るい色調で文様を描いたもの。五彩手は黒の輪郭線を用い、青、黄、緑、紫などの濃色で文様を描いたものである。
青手は、色使いは五彩手と似るが、素地の白磁の質がやや下がり、素地の欠点を隠すように、青、黄、緑、紫などの濃彩で余白なく塗りつぶした様式のものである。
これら古九谷と呼ばれる初期色絵作品群の産地については、戦前から1960年代にかけて「九谷ではなく佐賀県の有田で焼かれたものである」という説が主張されはじめた。
有田の山辺田窯(やんべたがま)、楠木谷窯などの窯跡から古九谷と図柄の一致する染付や色絵の陶片が出土していること、石川県山中町の九谷古窯の出土陶片は古九谷とは作調の違うものであったことなどから、「古九谷は有田の初期色絵作品である」との説が有力となった。

九谷焼の再興期
古九谷の廃窯から、約一世紀後の文化4年(1807年)に加賀藩が京都から青木木米を招き金沢の春日山に春日山窯を開かせたのを皮切りに、数々の窯が加賀地方一帯に立った。
これらの窯の製品を再興九谷という。 同じ頃、能美郡の花坂山で、新たな陶石が発見され今日まで主要な採石場となった。
これらの隆盛を受け、それまで陶磁器を他国から買い入れていた加賀藩では、文政2年(1819年)に磁器を、翌年に陶器を、それぞれ移入禁止にした。
再興期の窯元として春日山窯は京風、若杉窯は有田風、吉田屋窯は古九谷風を得意とした。春日山窯開窯以前の天明年間に、ほぼ同じ場所で越中国城端の焼物師、殿村屋和助という人物が窯を開いていた記録があるが、どのような焼物であったのかは、判っていない。
九谷焼中興の祖
九谷庄三(くたにしょうざ、文化13年(1816年)-明治16年(1883年)は、寺井村(現在の能美市寺井町)の農家に生まれた。17歳の時に小野窯に陶匠として招聘される。
後に窯業の指導に諸国から招かれるが、能登の火打谷(現在の志賀町)で、能登呉須と呼ばれる顔料を発見。後の九谷焼に多大な影響を与える。26歳で故郷に戻り寺井窯を開いた。
西洋から入った顔料を早い時期から取り入れ 彩色金欄手を確立し、庄三風と呼ばれる画風は後に西洋に輸出される九谷焼の大半に取り入れられることになる。
新九谷
明治時代に入り、九谷焼は主要な輸出品となり、1873年のウィーン万国博覧会などの博覧会に出品されると同時に西洋の技法も入り込んだ。
1872年頃から型押しの技術が九谷焼にも取り入れられ1892年頃から、獅子を始めとする置物の製作が盛んとなり、大正時代になると型が石膏で作られるようになり量産化が進んだ。
また、明治維新による失業士族の授産施設として1872年(明治5年)に誕生した金沢区方開拓所製陶部は、砂子吉平、初代諏訪蘇山等の参加を得て成果を上げ、1876年(明治9年)には、石川県勧業場と名を改めた。
1887年(明治20年)金沢工業学校(現在の石川県立工業高等学校)が開校し、次代の陶芸家が育成されるようになった。
現代の作家
二代浅蔵五十吉 (あさくらいそきち、1913年-1998年)文化勲章受章者。
吉田美統 (よしたみのり、1932年-)重要無形文化財保持者(人間国宝)
三代徳田八十吉 (とくだやそきち、1933年-2009年)重要無形文化財保持者(人間国宝)
伝統の「九角大皿」
九角の各稜を入隅にし、各辺に反りを持たせ、口縁をわずかに立ち上がらせて縁紅にするのが九角大皿の共通した特色。
見込みには円窓を付け、その内外に文様を付ける。古九谷様式の作品のなかでも数寄者の間で特に声価が高い大皿で、五彩子(色絵)に見られる独特の器形だ。
九谷焼の観光情報
 九谷焼協同組合
九谷焼協同組合
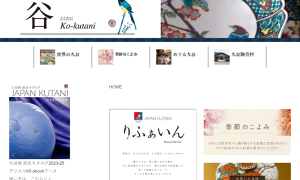


 石川県九谷焼美術館所蔵
石川県九谷焼美術館所蔵 石川県九谷焼美術館所蔵
石川県九谷焼美術館所蔵
